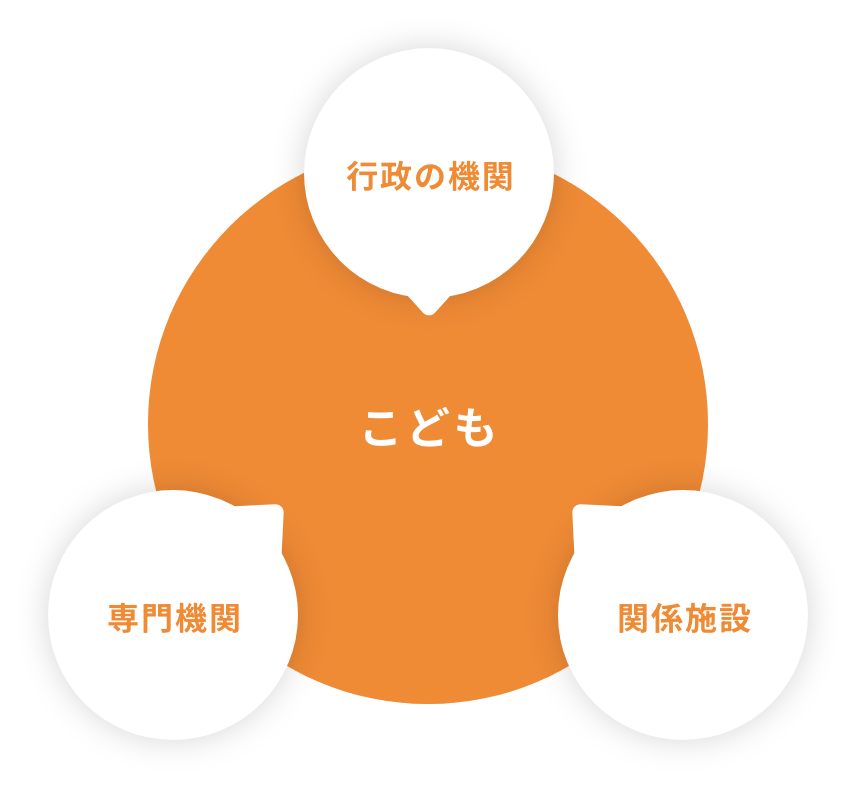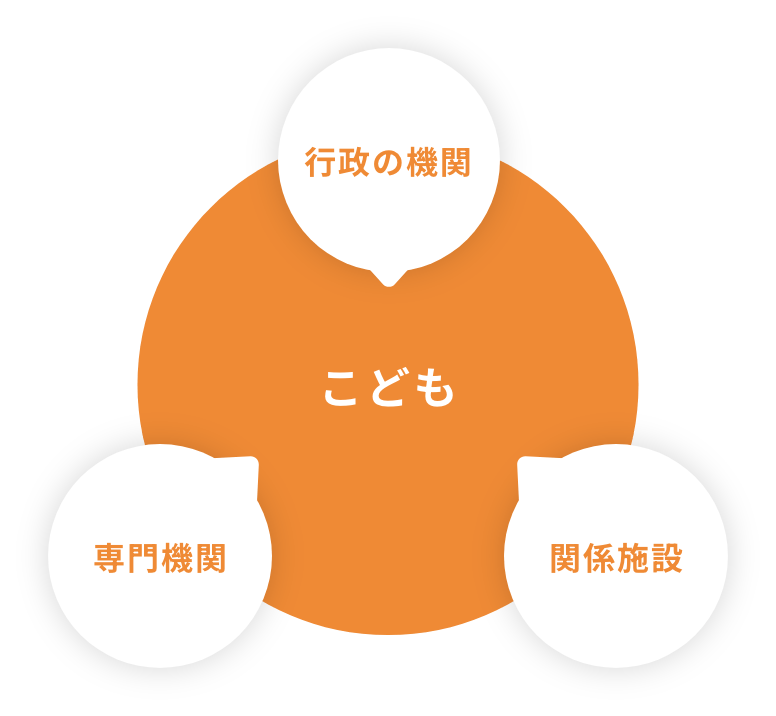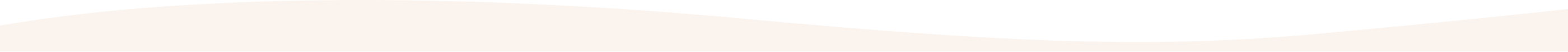

View 光楽園の中長期計画
これからの取り組み
地域まるごとファミリープロジェクト
地域まるごとファミリープロジェクトとは
「こどものいのちが輝く共生社会」の実現を目指し、光楽園が長期的に取り組んでいくプロジェクトです。
具体的には以下の3つの取り組みをおこないます。
1
ホームづくり
こどもの遊び・体験の場、
こどもと大人がつながる拠点
2
人・ネットワークづくり
保護者・地域の人々・
支援団体をつなぐ
3
連携支援チームづくり
行政機関・専門機関との
連携を深める
当面は、SDGs目標達成年度である2030年度に、北九州全域にこの取り組みが広がることを目指しています。
NPO法人光楽園のロジックモデル
私たちが目指す未来
こどものいのちが輝く共生社会を実現する
私たちの使命
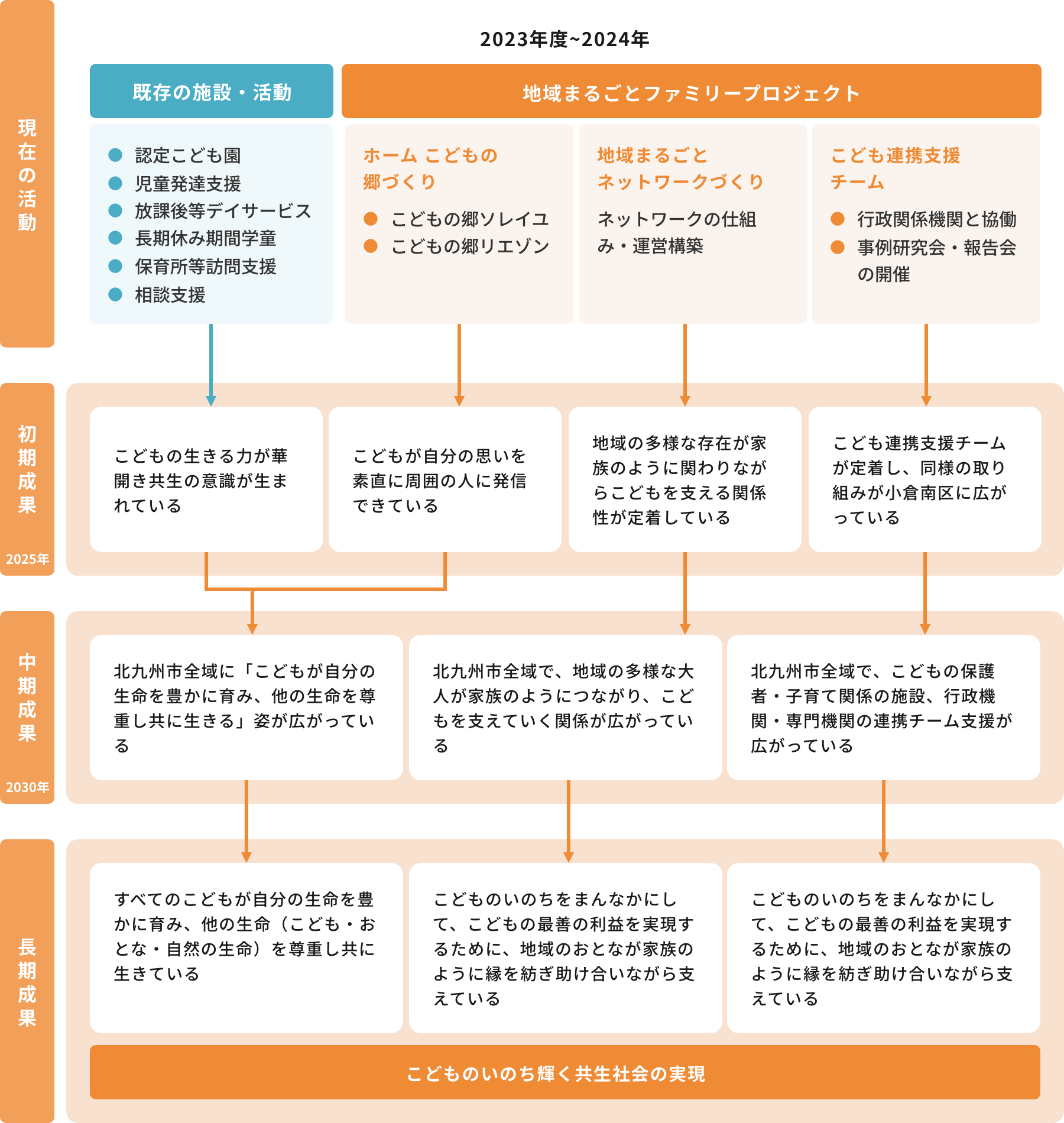
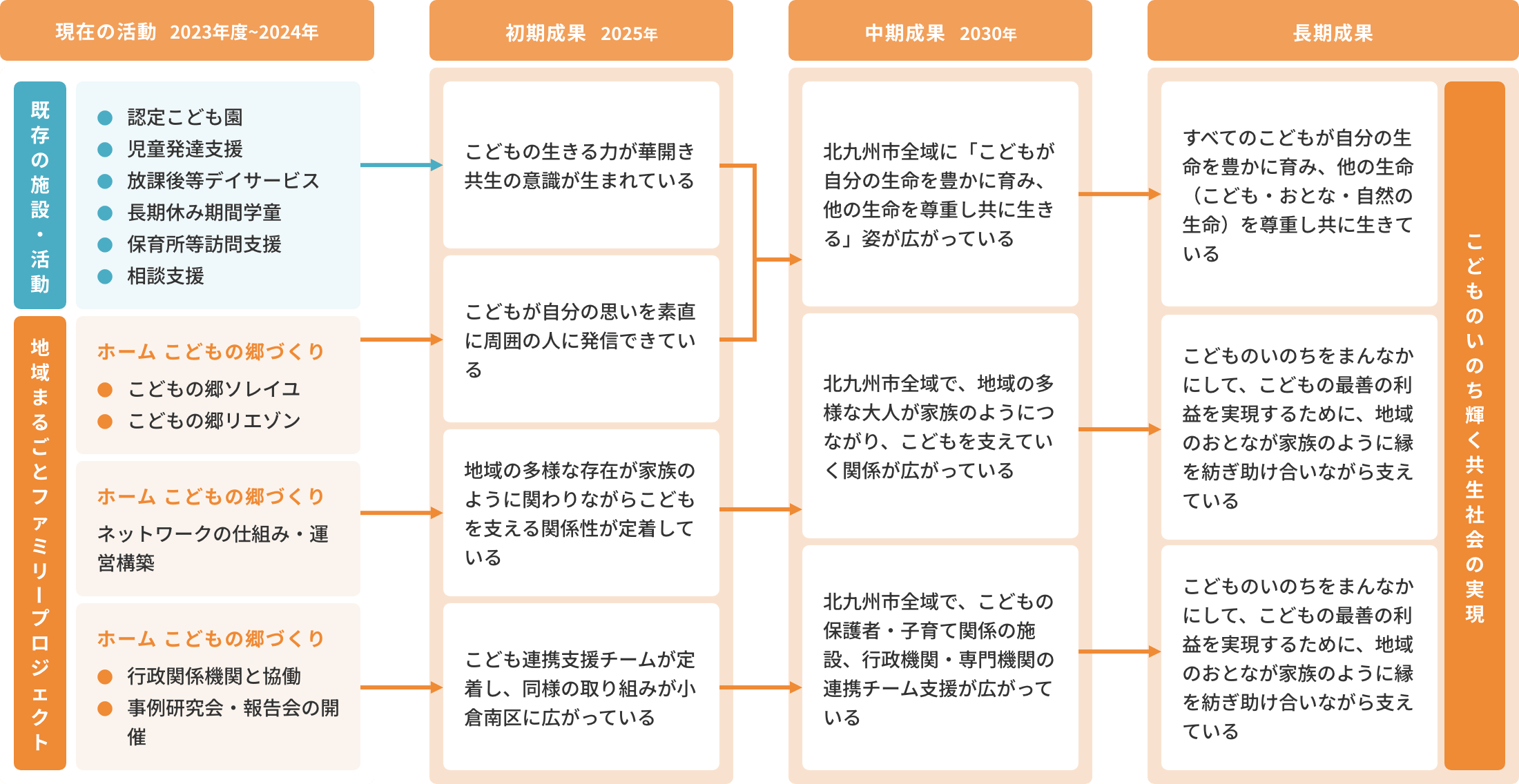
取り組み01
ホームづくり
こどもの郷ソレイユ
基本コンセプト
1
こどものいのちが輝く
共生社会の中核となる複合施設
2
すべてのこどもに自然遊びや
体験活動を保障する場所
3
自然との共生、
地域との共生の拠点
特徴
認定こども園と児童発達支援施設を併設していることで、発達障がい等の困りごとの有無に関わらず同じ場所で活動し、共に育ちあえる環境となっているため、こどもたちが自然に「多様な仲間と共に生きていく力」を育んでいくことができます。
- 認定こども園
おひさまいっぱい光楽園 - みんなの光楽園 そら
(児童発達支援 + 放デイ) - 【新設の施設】
地域子育て支援交流 にじ
豊かな自然環境と広くて自由に遊べる園庭で、夢中で遊びこみ、様々な体験をすることができます。
また、地域に開かれた施設=地域コミュニティの場なので、地域の方と多様な接点・繋がりができ、光楽園の経験やノウハウ・情報を地域子育て支援という形で還元できるほか、それ以外の情報交換や交流の機会も積極的に持っていきます。
こどもの郷リエゾン
施設移設等で空いた既存施設や近隣の空き家を活用・リフォームし、「制度の隙間で行き届きにくいこども支援」を実施する活動拠点「こどもの郷 リエゾン」を開所します。
リエゾンで実施する活動・支援予定
1
こどもショートステイ
2
日常的な食事支援
(朝食支援・朝食堂等)
3
不登校児の居場所づくり
4
家庭訪問支援等
アウトリーチ型支援の拠点
5
里親啓発活動等にも活用
取り組み02
人・ネットワークづくり
2024年度に光楽園の施設利用者・職員・OBや地域の関係者で形成するネットワークコミュニティ「地域まるごとファミリーネットワーク」を発足します。
ネットワークでは、光楽園の経験や知見、人材やインフラを有効に活用しながら、日常的な子育てに関係する情報交換、交流・学習イベントの企画・開催等を実施します。地域の子育て団体との連携や協働も行います。
制度のはざまで行き届かないこども・家庭支援の企画立案や実施も行います。
ファミリーネットワークのメンバーに積極的に里親啓発活動を続け、将来的に養育里親育成とその連携の仕組み作り等に着手します。
取り組み03
連携支援チームづくり
光楽園ができる支援や事業の範囲を広げていき、知見と力を蓄積していきます。
行政の機関(幼稚園こども園課・障害者支援課・児童相談所・療育センター・学校・スクールソーシャルワーカー等)・専門機関(発達支援センター・医療関係等)・関係施設と丁寧に関係性を紡ぎ、こどもをまんなかにした「チーム支援」の実践を積み重ねていきます。
チーム支援の取り組みの実践・経験を研究会・研修会の形式で行政機関・他団体などに共有し、取り組みを地域全体に広げていきます。